ホームセンターや自転車専門店などで見かける「ノーパンクタイヤ」という表示。
え!パンクしないの?
「そんな便利なタイヤがあるなんて」と思いますよね。
でも、、、、
・「ノーパンクタイヤ」ってどんな仕組み?
・本当にパンクしないの?
・パンクしない代わりに、修理になるとメチャクチャ費用がかかるとか?
と思っている人いませんか。
また、店頭には「ノーパンクタイヤ」の中に「パンクしにくいタイヤ」などと書かれた表示もありますよね。
「ノーパンクタイヤ」と「パンクしにくいタイヤ」では違うの?
こんなふうに思った人もいませんか。
「ノーパンクタイヤ」と「パンクしにくいタイヤ」は全然違う物です。
名前の通り、絶対パンクしないタイヤとパンクしずらいタイヤ、根本的にタイヤの構造が違います。
ではパンクしない「ノーパンクタイヤ」、こんな便利なタイヤいいですよね。
その代わりデメリットが実はあります。
なので、このデメリットが原因で普及しないという現実もあります。
今回は「ノーパンクタイヤ」の仕組みやデメリットについて解説していきます。
またパンク絡みの話しをしますが、自転車のトラブルで一番多いのがパンク、そのパンクの原因の7割近くがタイヤの空気が減ったまま走行しパンクしてしまうことが原因です。
例えば、道路のちょっとした段差を乗り越えようとした時、タイヤの空気圧が低下しているとタイヤが道路とホイールに挟まれ「リム打ち」というパンクを引き起こしたり、タイヤの中でチューブがねじれ摩擦によってチューブが破れパンクしてしまったりします。
自転車はパンクしてしまったらただの大きな荷物、通勤や通学途中、お出かけ先でパンクしてしまうと本当に困りますよね。
そんなトラブルを避けるために、やっておくべき4つの対策についても解説します。
この4つの対策をしておくことでパンクしずらくなり、もしもパンクしてしまってもすぐに対応出来て困ることは無くなりますので参考までに読んでみてください。

今回、解説する私は自動車関係の職に14年、クロスバイクに乗って10年以上。
毎日の通勤に自転車を利用しています。
電動キックボードや電動自転車などモビリティが好きで、モビリティーブログを開設して、みなさんにモビリティ情報を配信している者です。
どうぞよろしくお願いいたします。
「パンクしにくいタイヤ」と「ノーパンクタイヤ」とは


自転車販売店に行くと見かけるが「ノーパンクタイヤ自転車」や「パンクしにくいタイヤ使用の自転車」などの表示された自転車を見かけます。
「パンクしにくいタイヤ」とは?
タイヤの路面に接する部分が厚くなっておりガラス片などを踏んでもパンクしにくくなっていますが、ガラス片や画鋲ぐらいの物が刺さってもパンクしませんが、クギなど長い物を踏むとアウトです。
デメリットとしては、あまり効果が無いのとタイヤが硬いので空気圧低下が分かりずらいことです。
では、「ノーパンクタイヤ」とは?
ノーパンクタイヤは、空気を入れるチューブの代わりに特殊プラスチックやウレタンなどが使われているため、空気圧の確認をしなくても良くパンクしないというメリットがありますがデメリットもあり、あまり普及していないのが現状です。
なぜ、ノーパンク自転車は普及しないのか?
一番の問題が走行性能に問題が有ります。従来の空気入りタイヤは、タイヤの中のチューブに空気を入れることでタイヤを膨らませ支えています。軽い空気で支えるため軽量でクッション性が高く路面から伝わる振動もタイヤが軽減し乗り心地も良いので、長く運転しても疲れません。
一方ノーパンクタイヤの場合、チューブの代わりに特殊プラスチックやウレタンなどを使用しているノーパンクタイヤは従来の空気入りタイヤよりも固く、タイヤの重さも1~2kg重くなってしまいますので、タイヤが硬い分路面からの振動が伝わりやすく、重い分自転車の漕ぎ始めが重く遅くなり走行に支障が出るというおおきなデメリットがあります。
こんな理由から自転車のは不向きで、現在ノーパンクタイヤは産業車両や電動車椅子など電動で走行する乗り物に装着されていることが多いです。





高速走行しない電動の乗り物だったら適しているということですよね。
高速走行をしない悪路を走るマウンテンバイクは使われることが多いみたいですよ。
やっておきべき4つの対策
自転車のパンクトラブルに対して
これだけはやっておきたい
4つ対策を解説します。
これさえやっておけばパンクしずらくなり、万が一パンクしても慌てることなく対処できます。





何事も災害に対する準備が大切ですよね
スーパーバルブでエアー漏れ改善
自転車のタイヤには空気を入れるバルブという部分がありますよね。
そのバルブには3種類の形がありシティバイク(ママチャリ)やミニベロ、折りたたみ自転車など多くの自転車に使用されているタイプが英式というタイプのバルブ。
英式バルブは、バルブの開閉にゴムチューブを使っていて、ゴムチューブが劣化しやすく空気が漏れやすいというデメリットがあります。
このデメリットを改善するアイテムとして「スーパーバルブ」というバルブが販売されています。
「スーパーバルブ」は英式バルブを自動車やバイクに使われている米式バルブと同じ仕組みに変えることでデメリットを改善するアイテムです。





自分はクロスバイクに乗っていて、米式バルブですがエアー漏れも少なく10年間バルブ交換もしたことはありません。
また、自動車やバイクに使っているくらいなので、構造がしっかりしていると言えますよね。
これぞパンク回避の基本、空気圧点検のやり方
タイヤの空気は乗っても乗らなくても自然に減っていきます。
自転車や使っているタイヤの種類にもよりますが、最低月に一度、できれば3週間に一度くらい空気圧の点検をしているだけで、「パンクを70%以上回避できる」と言っていいほど、大切な作業です。
また、タイヤの空気圧はそれぞれ適正空気圧があり、正しい方法で適正範囲の空気を入れることでパンクを未然に防ぐことができます。
適正空気圧はタイヤの側面に表記してあり、「psi」「bar」「kgf」などの単位で表記しています。
詳しいことは下記の記事を参考にしてください。


タイヤポンプでおすすめしたいのが電動ポンプ。
バッテリー式で持ち運びができ、自動で空気を入れてくれるので、誰でも簡単に適正空気圧まで空気を入れることが出来ます。
アタッチメントが付いているので自転車だけでなく、自動車やバイク、ビーチボールや浮き輪、サッカーボールなど、あらゆる物に対応し日常的な場面でも使えるとっても便利なアイテムです。
是非一度使ってみてください。


空気入れを楽にする!!全自動スマート空気入れ【KUKiiRE】 ![]()
また、フロアタイプのポンプは圧力計付きをおすすめします。
パンクしてしまった時の応急処置
出先でパンクしてしまった!
「どうしても乗って行きたい」という時に便利なアイテムがパンク修理剤。
小さな穴が原因であれば、空気と一緒にパンク修理剤を入れることで穴がふさがり、すぐに乗り出すことが出来ます。
自転車に常備していると便利なアイテムです。
詳しいことは、下記で解説していますので参考にしてください。


「困った」という時の対処法
パンクや故障で自転車が走行不能になってしまい、
「家まで引いて帰るのは、辛い!困ったな~!」こんな時に入っていて良かったと思うのが自転車ロードサービス、規定距離範囲であれば無料で家や自転車修理店などに運んでもらえます。
また、賠償責任保険も付いているので交通事故によるケガも安心。
例えば自転車事故を起こし走行不能になった時に、相手への賠償責任も自分の自転車搬送も電話をすれば対応してもらえるので安心です。
月換算384円から加入できて、義務化されている自転車保険にも対応しています。
詳しい解説は、下記の記事を参考にしてください


この機会に加入を検討してみてはいかがでしょうか
おすすめ自転車ロードサービス公式サイト
まとめ
タイヤのパンクは、故障に関する自転車トラブルで最も多いトラブルです。
「ノーパンクタイヤ自転車」や「パンクしにくいタイヤ」は、改善する点があり便利で優れたタイヤとは言えないと思います。
パンクをできるだけ回避し対処する為にも、今回紹介した4つの対策
・スーパーバルブへの交換 英式バルブのデメリットを無くせます。
・空気圧の点検 パンクしない為にも、これだけはやっておきたい点検!
・パンク修理剤 応急処置に最適
・ロードサービス 出来れば加入しておきたい保険、自転車保険義務化にも対応。





僕は、この4つことを10年以上実行しています。
パンク修理剤は過去に2回使ったことがあります、結局なにが原因か分からなかったけど。
ロードサービスは一度も使ったことはありませんが、御守り代わりとして、自転車保険は「あ!」と思う接触事故になりそうなことがありますので、おすすめします。
突然ですが、自転車保険の義務化について知っていましたか?
近年、高額な損害賠償請求される事例が多くなり、損害賠償保険のは加入しておくことをおすすめします。
自転車保険のことや義務化については、下記の記事を参考にしてください。
万が一に備えて快適な自転車ライフを過ごしましょう。
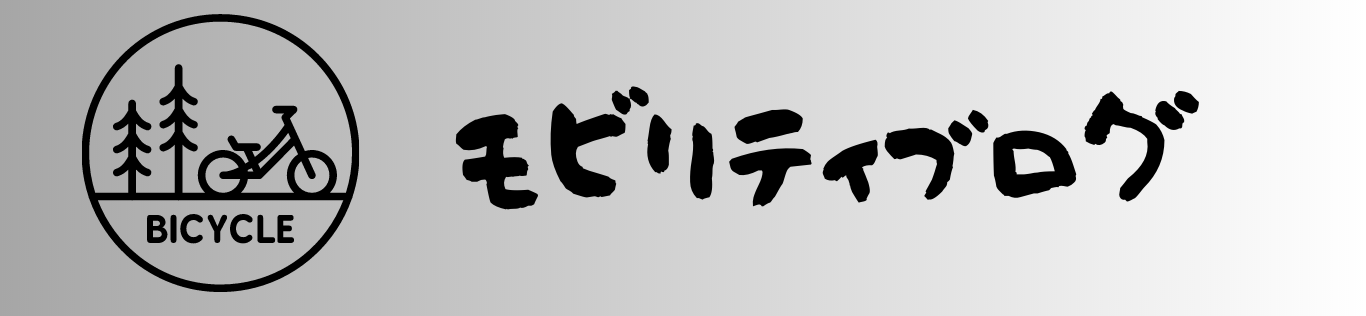



コメント