当記事は、数年に渡り電動キックボードシェアサービスの実証実験などを参考に法改正されて来た電動キックボード等の交通ルールについて最終的に閣議決定した道交法を詳しく解説していきます。
・そもそも電動キックボード等の法改正の内容とは?
・法改正はいつから実施されるのか?
・免許やヘルメットは必要なのか?
などを掘り下げて解説していきます。
次世代モビリティーとして海外では普及が進む電動キックボード、
日本でもコロナ過の中、電動モビリティー(移動手段)として注目されるようになり、
街でも電動キックボードに乗る人を見かけるようになりましたが、
その一方、違法走行をする人も増え、取り締まりや逮捕のニュースも増えました。
現在日本では、電動キックボードは原動機付自転車と同じ扱いで
原付免許を取得し、走行する際はヘルメットの着用を義務付けられています。
そして走行出来るのは、車道のみです。

じゃあ、法改正で何が変わったの?

今回の法改正では、新しい区分として特定小型原付自転車という枠が設けられ、性能について認定された車種については16歳以上であれば、免許不要でヘルメットの着用は努力義務で公道走行できるようになったんだ。
それでは解説していくね。
法改正実施はいつから?
現行、公道走行可能な電動キックボード等は原付扱いになって運転する時は、原付免許証やヘルメット着用などが必要ですが、法改正により2023年7月1日からは新たに特定小型原付自転車という区分が設けられ、条件を満たしている電動キックボード等は16歳以上であれば免許不要でヘルメットは努力義務で運転することが出来ます。
ヘルメットの努力義務とは?
強制ではなく「出来るだけ着用してください」という事。
なので、警察に注意はされるかもしれませんが、違反では無いということ。
ただし今後、本当に事故を起こして怪我をした場合に保険などの過失という責任の部分で関わってくる可能性はあります。
特定小型原付自転車とは

電動キックボード等は、最高速度が自転車と同程度であるなど下記のような条件を満たしている車体が特定小型原付自転車として走行場所が自転車と同じになるなどの新しいルールが適応されます。
| 最高速度 | 20km/h以下 |
| 車体サイズ | 長さ190cm以下 幅60cm以下 |
| 定格出力 | 0,6キロワット以下 |
この特定小型原付自転車には、電動キックボードだけでなく条件を満たしている電動バイクのような車種も対象になります。

規制緩和によって変更する内容
| 改正前 | 改正後 | |
| 免許証 | 必須 | 不要 |
| ヘルメット | 必須 | 努力義務 |
| 自賠責保険 | 必須 | 必須 |
| ナンバープレート | 必須 | 必須 |
| 最高速度 | 30km/h | 通常モード20km/h 歩道モード6km/h |
| 走行場所 | 車道のみ | 車道、自転車レーン、路側帯 |
| 年齢 | 16歳以上 | 16歳以上 |
特定小型原付自転車の公道可能条件
保安基準
今回の特定小型原付自転車の保安基準は図のような項目になります。

今までの公道走行可能な電動キックボードの保安基準との大きな違いは、バックミラーがないこと、最高時速表示灯が装備された点です。
新しく開設された性能認定制度
新しく特定小型原付自転車には、性能認定試験という制度が開設されました。

この制度では、国土交通省がその能力を審査し、民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該車種の保安基準適合性等を確認します。保安基準適合性等が確認された車種には、メーカー・確認機関を明記した上記のようなシールを車体に貼ることができます。
このシールが付いている車種は保安基準を満たしている一つの目安になります。
走行できる場所



特定小型原付自転車は最高速度を切り替えることによって、車道、路側帯、自転車レーン、歩道を走行することが出来ます。
走行モードの変更は、識別灯の点灯の仕方によって見分けることが出来ます。
| 通常モード | 最高速20km/h | 車道、自転車レーン、路側帯 | 緑点灯 |
| 歩行者モード | 最高速度6km/h | 歩道自転車走行可能エリア、路側帯 | 緑点滅 |
その他、通行禁止場所については現行と同じで道路標識等で禁止されている道路については通行できません。

自賠責、ナンバープレートの加入
自賠責については改正後も加入が義務づけられていますが、令和6年4月以降は特定小型原付自転車のための新しい保険料が適応される予定です。
この時に現行の保険料より安くなる場合については、申請すれば差額が返還される予定です。
また、ナンバープレートについても現行と同じで、各自治体の条例等で定めるところによりナンバープレートを取得しなければなりません。
ただし、安全対策として現行のナンバープレートよりも小さくなる予定です。
その時に従来のナンバープレートを取得している場合でも、小型のナンバープレートに変更することができます。
安全面からも小型のナンバープレートに変更するようにしましょう。

現行の自賠責やナンバープレートの取得方法については、下記で詳しく開設しています。
電動キックボードの現行ルールと保安基準
現行の道交法では、電動キックボードは原付扱いです。
下記の点が取得、適合などをしていなければなりません。
| 原付免許証 |
| 自賠責保険加入 |
| ナンバープレートの取得 |
| 公道走行可能な保安基準適合車 |
| ヘルメット着用 |
走行できる場所も原付バイクと同じ車道のみ、最高時速30km/hで下記のような保安基準を満たしていなければまりません。


装備が一つでも欠けている状態で公道走行すると、自己責任において罰則の対象になります。
その場合、3が月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
電動キックボードの試乗、購入は?
「電動キックボードには、興味があるけど購入には悩む」
「本当のところ、安全面や乗り心地などはどうなの?」
と思う人もいるのではないでしょうか。
まずは、試乗してみてください
試乗は電動キックボードシェアサービスを利用し、体験できます。
また、早くもネット販売にて特定小型原付自転車に対応した電動キックボードの予約販売が始まっています。
比較的に低価格で購入できますので、こちらもチェックしてみてください。



まとめ
数年に渡り、電動キックボードシェアサービスの実証実験などを参考に法改正をして来た電動キックボードの道交法、最終的に特定小型原付自転車という新しい枠を作り、始動していくことに決定しましたが、この決定には安全面などに賛否があり一時ニュースなどで話題になりました。
電動キックボードは移動手段として、とっても便利な乗り物で海外では人気が高く色々な場面で広く利用されています。
現状の日本の交通ルールでは、まだまだ課題がたくさんありますが次世代の便利な乗り物として普及していくのではないでしょうか。
何度かシェアサービスで利用したことがありますが、楽しくとても便利な乗り物ですよ。
一度試乗、体験してみてください。
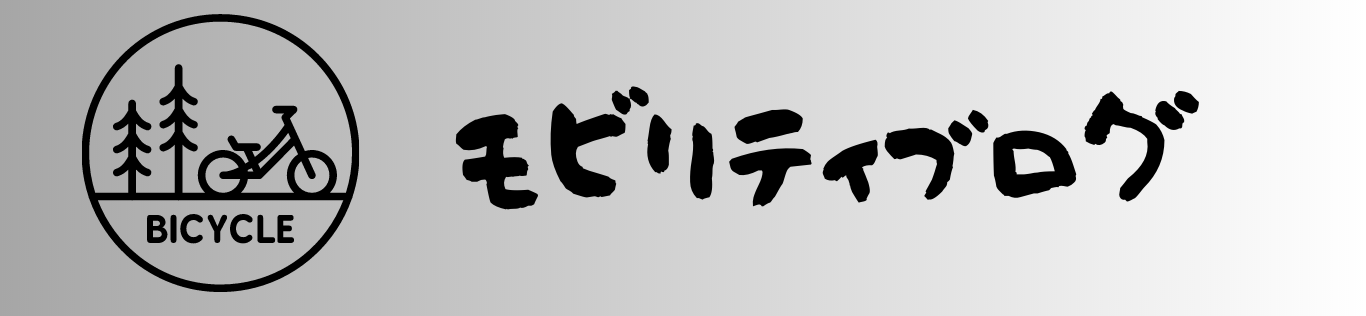




コメント